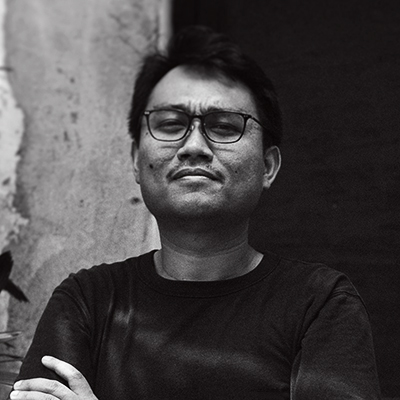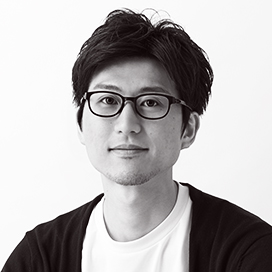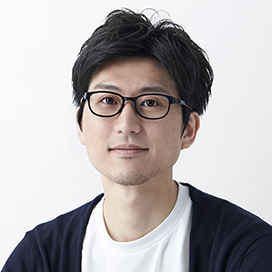About YouFab
常識に挑む。常識に抗する。
常識をHackする。
そんなスピリットに溢れた挑戦に、
YouFabは強く期待します。
Conviviality
古いOSと新しいOSのはざまから
生まれ出てくるもの
世間を騒がせている事件や騒動を見ていると、古い時代のシステムがいよいよ限界を迎えているのだなという思いを新たにする。それがビジネスに関わることであろうが、文化に関わることであろうが、政治に関わることであろうが、小手先のアップデートではもはや対応できないような困難が次から次へと表出しては、システム全体の限界がさらに明らかになっていく。小さな問題だと思って改善に手をつけはじめたら、芋づる式に業界や産業全体のあり方の問題、法体系の問題、あるいは根深いマインドセットの問題に行き着いてしまい、結局のところ問題のありかを見失ってしまうのは、ありがちなことだ。
アプリを新調すれば済むと思っていたところ、OSそのものをアップデートしないとダメだ、ということが明らかになってしまう、という感じだろうか。OSのアップデートは自分のパソコンですらめんどくさいものだ。それが会社や業界や産業の、ひいては社会全体に関わるOSともなれば、簡単にアップデートできると思うほうがおかしい。当然、さまざまな軋轢が噴出することにはなる。
さらにいえば、いざOSをアップデートしましょうとなったところで、古いシステムに取って変わる新しいOSというものは、その辺で売りに出されていてとりあえずそれを購入してダウンロードして一丁あがりというものではない。そのOSは、考えながら実験され、実装されてはまた検証され、また実験され、といういつ終わるとも知れないサイクルのなかで、徐々にその姿を表してくるようなものにならざるを得ない。最初に全体を見回して、精密な設計図を書いて、それが万全であることを見越した上で実装する、という手順は、そこでは通用しないというのが大きな悩みの種となる。あらゆるアップデートは、「とりあえずやってみよう」というものにならざるを得ないのだ。
とすれば、当然、あっちは改善されたけど、こっちに新たな問題が出てきた、とか、こっちばかりが改善され、あっちはおろそかになった、といったことも出てこざるを得ない。これだけ複雑な世の中になっているのだ。いっぺんに一気に全部カタをつけることは、どう考えても至難のワザだ。であればこそ、わたしたちは当面しばらくの間、というか、いつ終わるとも知れないアップデート期間を、とても不安定な状況のなかで過ごさざるを得ないことになる。
それはとても不安で怖いことだ。不安で怖いので、あっちが改善されてもこっちはどうなんだ、といったひとつひとつの不満や矛盾が、軋轢や対立となって社会をどんどん分断していくことになる。そして、そんななかで、わたしたちは、自分がよりよく生きていくために必要な手立てや手助けを見失っていくことにもなる。
イバン・イリイチという思想家・歴史家が、コンヴィヴィアリティという考え方を、提唱したのはたしか1970年代のことだった。すでにその頃から、いまの国家や社会を動かすOSには限界が来ていることは察知されていて、それを乗り越えるための考え方、態度として、イリイチはコンヴィヴィアリティという概念を世に問うたのだった。
それは、自立共生、自律協働などと訳され、簡単に言えば、なんらかの困難や課題に直面する人やコミュニティが、自分たちの手でそれを改変・改革し、持続的に維持することができるようなシステムや制度や道具のあり方を模索するものだ。身近にある課題に、政府や産業が取り組んでくれないのであれば自分たちでやろう、ということだ。OSの例で言えば、Linuxの考え方の根底にはコンヴィヴィアリティの思想が流れている。
できるだけ外部に頼らずに、自分たちの生活を自立/自律させること。そのための仕組みや制度、道具は、いまもこれからも、ありすぎて困るということは決してないはずだ。むしろ、そうしたものが数多く社会のなかに実装され、それらが相互的にやりとりができるようになって社会全体に行き渡り始めたときに、わたしたちは、これまでの古いものとは違う、新しいOSというものの輪郭を知ることになるのだろう。
これだけ世の中が騒々しくもなってくれば、テクノロジーの進展が、いったい誰のための進展なのかということについて、開発者やクリエイターが、今一度真剣に考えるのは責務だろう。世の中便利になればそれで豊かさは自動的に実現できるのである、という発想は、すでにして古いOSのシステムのなかでの論理でしかない。
その論理からこぼれ落ちるものがいたとして、それでも安全に人の生活やコミュニティが持続できるような仕組みを、わたしたち全員が、よほどアタマを使って考えなくてはならない。

若林 恵
編集者
1971年生まれ。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。
早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業後、平凡社入社、『月刊太陽』編集部所属。
2000年にフリー編集者として独立。以後,雑誌,書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。
音楽ジャーナリストとしても活動。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。
2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。著書『さよなら未来』(岩波書店・2018年4月刊行)。
Organized by FabCafe
Tokyo、Kyoto、Hida、Taipei、Bangkok、Barcelona、Toulouse、Strasbourg、Monterrey、HongKong。FabCafeは、現在世界10拠点に広がるCreators’ Cafeネットワーク。そこでは、日々エリアのユニークなクリエーターが集い、出会い、才能を競い合い、発表の場を共有しています。誕生以来、世界10箇所に広がった拠点は、美味しいコーヒーと居心地の良いスペースと同時に、クリエイティブWorkshopやイベントを通じて、15000を超えるアイデアの誕生をサポートしてきました。
YouFab Global Creative Awardsは、その年間活動の集大成。それぞれの拠点キュレーターがその1年に出会ったクリエーターに声をかけて作品を集めると同時に、広くオープンに告知し世界中で生まれたユニーク作品の中から、次の時代を変えていくであろうクリエーターを発見し、応援していく活動です。
これまで数多くの受賞者が、YouFabの受賞を通じてGlobalにつながり、活躍の場を広げてきました。
From Local to Global, Global to Local。
次の時代の才能は、先端研究拠点や大学のラボだけでなく、世界の小さな町のコミュニティからもきっと生まれていくと私たちは信じています。 LocalからGlobalへの発信とその成果のLocalへの還流。そのサイクルを通じてYouFabは、世界のクリエイティブが、そしてクリエイティブビジネスがさらに面白くなっていくことをサポートしていきます。

福田 敏也
博報堂フェロー/Chief Creative x Technology Officer
大阪芸術大学デザイン学科教授
株式会社トリプルセブン・クリエイティブストラテジーズ代表取締役
FabCafe 共同設立者
多様なメディアでの Communicationをplanning / direction / consultingする。自らの会社777interacitiveでは企業の先端ニーズにこたえ、FabCafeではものづくりの未来を考え、博報堂では次世代型Creatorを育成し、大阪芸術大学ではDigitalDesign教育にあたっている。海外評価も高く世界のデザイン賞で多数の受賞歴と審査経験をもつ。